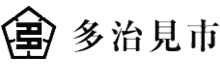ここから本文です。
更新日:2023年4月3日
給付
療養の給付
医療機関などに通院・入院したときや医師の指示のもとで訪問看護ステーションなどを利用したときに、保険証を提示すると費用の一部を自己負担するだけで、診療を受けることができます。
自己負担割合は、以下のとおりです。
- 義務教育就学前:2割
- 義務教育就学後、70歳未満:3割
- 70歳以上75歳未満:3割または2割
一部負担金の減免等について
災害や事業の休廃止など特別な事情により収入が一定額以下になり、医療機関などに支払う一部負担金の支払いが困難になったとき、減免や支払猶予を一定期間受けられる場合があります。詳しくは保険年金課へお問い合わせください。
療養費
以下の場合は、診療費などの全額をいったんお支払いいただいた後、申請により自己負担割合を除いた金額が国保から払い戻しされます。
- 旅先での急病やけがなど、やむを得ない事情で保険証を持たずに診療を受けたとき
- 療養のため医師の診断により補装具・コルセットを製作したとき※
- 医師の診断により、あんま、はり・きゅう、マッサージ、柔道整復の施術を受けたとき
- 輸血を受けたとき※
- 海外渡航中に診療を受けたとき※
医師が必要と認めた場合のみ適用されます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 領収証
- マイナンバーカード等個人番号の分かるもの(世帯主及び受診者)
- 医師の診断書(施術内容の証明書)
- 預金口座番号が分かるもの(被保険者本人または世帯主)
- 受診者のパスポート(海外療養費申請時)※注1
- 調査に関わる同意書(海外療養費申請時)※注2
- 外国語の場合は、その翻訳文も必要になります(翻訳者の住所、署名入りのもの)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券等)
注1・注2海外療養費の支給申請に対する審査の強化について
海外療養費につきまして、昨今の海外療養費の不正受給に関する報道及び厚生労働省通知により、受付審査を強化いたします。つきましては、下記のとおり対応してまいりますのでご協力の程よろしくお願いします。
- 海外療養費の支給申請に係る療養などが、渡航期間内に行われたものであることを確認するため、パスポートの提示をお願いします。この際、パスポートの写しを窓口で取らせていただきます。
- 申請内容について現地医療機関等へ事実調査するための同意書が必要です。
- 不正請求と判明したもの、あるいは不正請求と認めるには至ってないものの疑いがあると判断した場合、警察と連携して厳正な対応を行わせていただきます。
海外療養費支給申請に必要な様式
出産育児一時金
直接支払制度(受取代理制度)を利用する場合
- 出産費用が50万円を超える場合は、その差額を自己負担することになります。
- 出産費用が50万円に満たない場合は、残った差額を世帯主の口座に振り込みます。
受取代理制度を利用する場合は出産予定日の2ヶ月前から出産日までの間に申請が必要です。
直接支払制度(受取代理制度)を利用しない場合
- 出産費用の全額を一旦、自己負担することになります。
- 出産育児一時金は世帯主の口座に振り込みます。
制度対象外分娩について
制度対象外分娩(産科医療保障制度に未加入の医療機関での出産、海外出産、自宅出産など)の場合、産科医療補償額1万2千円を控除した48万8千円の支給となります。
申請に必要なもの
- 保険証
- 母子手帳
- 預金口座番号が分かるもの(世帯主のもの)
- 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書
- 直接支払制度利用の有無が確認できる書類
- 死胎埋火葬許可証または医師の証明書(死産・流産の場合)
- 出生証明書(海外出産の場合)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券等)
移送費
疾病や負傷により移動が著しく困難な場合に、医師の指示により保険診療を受けるため病院や診療所に緊急に移送されたときは、申請して認められたものについて移送費が支給されます。通院のための交通費は対象外になります。
申請に必要なもの
- 保険証
- 領収証
- 預金口座番号が分かるもの
- 医師の証明書
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券等)
葬祭費
国民健康保険の加入者が死亡したときは、葬祭を行った人(喪主または施主)に葬祭費として50,000円が支給されます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 会葬はがきや葬儀の領収書など、喪主または施主の氏名が確認できるもの
- 喪主または施主の預金口座番号の分かるもの
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券等)
申請先
市役所保険年金課または各地区事務所
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
保険年金課給付グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5762(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2171~2174
ファクス:0572-25-7286