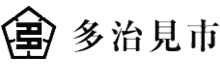ここから本文です。
更新日:2025年11月4日
保険料
納付義務者
保険料を納める人は、各世帯の世帯主になります。
世帯主が国民健康保険の加入者でなくても、その世帯の中に1人でも国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主を納付義務者とみなします。
保険料の計算方法
国民健康保険の保険料は、「医療分」、「後期高齢者支援金分」、「介護分(40歳~64歳)」のそれぞれを、所得割・均等割・平等割で計算し、その合計額で決まります。
多治見市の保険料は、次の方法で世帯ごとに計算します。
令和7年度の保険料の料率及び賦課限度額(年額)
|
所得割 (所得に応じて計算) |
均等割 (加入者数に応じて計算) |
平等割 (1世帯あたりで計算) |
賦課限度額 (1世帯の保険料の最高限度額) |
|
|---|---|---|---|---|
|
医療分 |
世帯の基準総所得金額×7.65% |
1人につき 31,400円 |
1世帯につき 22,300円 |
660,000円 |
|
後期高齢者支援金分 |
世帯の基準総所得金額×2.73% |
1人につき 10,900円 |
1世帯につき 7,700円 |
260,000円 |
|
介護分 (40歳~64歳) |
40歳~64歳の加入者の基準総所得金額×2.20% |
1人につき 11,000円 |
1世帯につき 5,800円 |
170,000円 |
(注)基準総所得金額…前年の総所得金額から、基礎控除額(1人43万円まで)を引いた額
途中加入・脱退の場合の保険料
年度途中で加入
年間保険料(12か月分)×加入資格発生月から3月までの月数÷12
保険料は、届け出をした時点からではなく加入資格が発生した月の分から納めることになります。
年度途中で脱退
年間保険料(12か月分)×4月からから3月までの間で加入していた月数÷12
- 世帯全員が脱退した場合、前月分までの保険料を再計算します。その結果、不足分がある場合は、脱退した月以降に賦課する場合があります。納め過ぎとなっている場合は、後日、還付します。
- 世帯の一部の人が脱退した場合、再計算して、残額を月割りで計算します。
保険料の軽減・減免
保険料軽減制度
世帯の前年中の所得が一定基準以下の場合は、均等割額と平等割額が軽減されます。くわしくは、保険年金課にお問い合わせください。
| 軽減率 | 対象世帯の前年所得 |
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 5割軽減 | 43万円+30.5万円×(被保険者数※)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 2割軽減 | 43万円+56万円×(被保険者数※)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
(注)同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。
未就学児の被保険者均等割額の軽減(令和4年度から)
国民健康保険に加入する未就学児の均等割額が5割軽減されます。上記の「保険料軽減制度」に該当する世帯については、軽減(7割、5割、2割)後に、さらに未就学児の均等割額を5割軽減します。このため、未就学児の均等割額は、7割軽減が適用される世帯では8.5割軽減、5割軽減が適用される世帯では7.5割軽減、2割軽減が適用される世帯では6割軽減となります。
ただし、未就学児の均等割額が軽減されても、なお、世帯の年間保険料額が最高限度額に達するときは、最高限度額が保険料額となります。
産前産後期間の保険料減額(令和6年1月分から)
出産する被保険者の方の産前産後期間にかかる所得割額と均等割額を減額します。くわしくは、「産前産後期間の国民健康保険料の減額について」を、ご覧ください。
非自発的失業者軽減制度
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)である場合は、保険料が軽減される可能性があります。くわしくは、保険年金課へお問い合わせください。
減免制度
災害で大きな被害を受けたときや、傷病等により前年と比較して収入が大幅に減少したことにより生活が著しく困窮し保険料を納めることが困難な場合は、申請により、一定の基準で保険料が減免になることがあります。くわしくは、保険年金課にお問い合わせください。
お問い合わせ
保険年金課年金国保グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2162~2164
ファクス:0572-25-7286