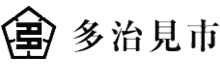ここから本文です。
更新日:2024年10月4日
児童手当
児童手当の制度改正(拡充)と新しく対象となる方へ申請のお願い(PDF:123KB)
令和6年9月30日付け多保第1151号にてお送りした「児童手当・特例給付 支払通知書」は、制度改正前の内容になります。今後11月下旬に制度改正後の内容が反映された支払通知書を発送します。制度改正後の内容については、その通知にてご確認ください。
目的
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するため、支給されるものです。
児童手当の支給を受けた方は、制度の趣旨に従って手当を用いなければならないことが責務として定められています。
支給対象者
(1)支給対象者
日本国内に住所を有し、対象児童を養育している次1~7のいずれかに該当する方が支給対象者となります。
- 父と母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い方(※1)
- 父母等に養育されていない、あるいは、生計を同じくしていない児童を養育している方(養育者)
- 未成年後見人
- 父母が海外に居住し、その児童を養育している祖父母等で、父母から指定を受けている方
- 離婚協議中であり、児童と同居している父又は母(配偶者と同住所の場合、世帯分離が別途必要。)
- 児童福祉施設等の設置者(2か月以内の短期入所又は通所を除く。)
- 里親(2か月以内の短期委託を除く。)
(※1)生計を維持する程度の高い方とは、父母のうち恒常的に所得の高い方を指します。
(2)支給対象者でない方
- 児童が海外に居住(留学など一時的な場合を除く。)している場合
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
(3)注意事項
- 支給対象者となられる方が、公務員(独立行政法人を除く。)の場合は、所属庁の長が児童手当・の支給を決定します。直接職場へお問い合わせください。
- 外国籍の方は、多治見市に住民票がない場合、児童手当の支給ができません。(住民票が作成されるのは、特別永住者・中長期在留者等の日本人の配偶者や定住者等、3か月を超えて適法に日本に在留する者に限られます。)
対象児童
日本国内に住所を有し、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童が対象となります。
支給月額(児童1人あたり)
児童の年齢や養育する児童の人数、支給対象者の所得額により、下表のとおりとなります。
|
児童手当 |
||
|
第1子 第2子 |
第3子
|
|
| 3歳未満の児童 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳以上の児童及小学生 | 10,000円 | 30,000円 |
<児童出生順位(第○子)の数え方>
請求者(受給者)が監護する児童で、22歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童を年齢の高い児童から順に「第○子」と数えます。
支給月額の計算例
19歳、11歳、5歳の児童がいる場合
|
児童の年齢 |
支給月額 |
|
| 第1子 | 19歳 | 0円 |
| 第2子 | 11歳 | 10,000円 |
| 第3子 | 5歳 | 30,000円 |
| 支給月額の合計 | 40,000円 | |
19歳の児童は、児童手当・特例給付の支給対象ではありませんが、児童の数に含めます。
20歳、11歳、5歳の児童がいる場合
|
児童の年齢 |
支給月額 |
|
| 第1子 | 20歳 | 0円 |
| 第2子 | 11歳 | 10,000円 |
| 第3子 | 5歳 | 30,000円 |
| 支給月額の合計 | 40,000円 | |
20歳の児童は、児童手当の支給対象ではありませんが、児童の数に含めます。
21歳、17歳、15歳、12歳の児童がいる場合
|
児童の年齢 |
支給月額 |
|
| 第1子 | 21歳 | 0円 |
| 第2子 | 17歳 | 10,000円 |
| 第3子 | 15歳 | 30,000円 |
| 第4子 | 12歳 | 30,000円 |
| 支給月額の合計 | 70,000円 | |
21歳の児童は、児童手当の支給対象ではありませんが、児童の数に含めます。
22歳、17歳、15歳、12歳の児童がいる場合
|
児童の年齢 |
支給月額 |
|
| 第1子 | 22歳 | 0円 |
| 第2子 | 17歳 | 10,000円 |
| 第3子 | 15歳 | 30,000円 |
| 第4子 | 12歳 | 30,000円 |
| 支給月額の合計 | 70,000円 | |
22歳の児童は、児童手当の支給対象ではありませんが、年度末まで児童の数に含めます。
23歳、17歳、15歳の児童がいる場合
|
児童の年齢 |
支給月額 |
|
| - | 23歳 | 0円 |
| 第1子 | 17歳 | 10,000円 |
| 第2子 | 15歳 | 10,000円 |
| 支給月額の合計 | 20,000円 | |
23歳の児童は、制度上第1子にならないため、17歳の児童を第1子として、児童の数を順に数えます。
支給時期
- 原則として「10月」「12月」「2月」「4月」「6月」「8月」に、それぞれ前月分までの手当が支給されます。
- 各支払月の15日(土・日曜日・祝日の場合は、直前の開庁日)に、指定された預金口座に振込みます。
- 振込みが行われる時間は、金融機関によって異なりますが、振込日には指定の口座に振込まれます。(午後になることもあります。)
| 振込月 | 振込の内訳 |
| 10月 | 8月分~9月分 |
| 12月 | 10月分~11月分 |
| 2月 | 12月分~1月分 |
| 4月 | 2月分~3月分 |
| 6月 | 4月分~5月分 |
| 8月 | 6月分~7月分 |
手続きの方法
(1)新規認定手続き
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、新規認定請求の手続きが必要になります。
手当の支給は、原則として請求する日の属する月の翌月分からとなります。ただし、出生や他市区町村からの転入の場合は、出生日又は前住所地における転出予定日の翌日から15日以内に新規認定手続きを行うことで、出生日や転出予定日等の属する月の翌月分から手当が支給されます。(15日特例)
申請に必要な書類や確認書類
- 認定請求書
- 請求者名義の金融機関預貯金口座(通帳など)がわかるもの
- 請求者の健康保険証の写し
- 請求者及びその配偶者の個人番号(マイナンバー)関係書類
その他新規認定に必要な添付書類等
ア.児童と別居している方
- 別居監護申立書(※1)(※2)(※3)
(※1)児童の住所が市外の場合は、児童の個人番号(マイナンバー)関係書類が必要です。
(※2)児童居住世帯における世帯主の署名が必要となります。
(※3)18歳になって3月31日までの間にある児童は別居監護申立書の提出が必要です。
イ.18歳年度末から22歳年末までの児童がいて且つ3人以上児童がいる方
・監護相当・生計費の負担についての確認書(※1)(※2)(※3)
(※1)監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
(※2)生計費の相当部分を負担していること
(※3)18歳年度末から22歳年末までの児童の提出が必要です。
ウ.離婚協議中であり、児童と同居している父又は母
- 児童手当の受給資格に係る申立書
- 離婚協議中であることがわかる書類(※1)
(※1)「協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本」「調停期日呼出状(離婚)の写し」など離婚の意思表示が相手方になされていることが確認できる書類
エ.海外から入国された方
- 入国された方のパスポートの写し(顔写真及び入国した日がわかるスタンプのあるページの写し)
転入された方に配偶者や児童も含む場合には、全員分のパスポートの写しが必要です。
(2)その他、養育している児童の人数変更や口座変更等の手続き
該当となる場面や養育する児童数に応じて手続きに必要な書類が異なります。下表の場面に該当するものがない場合や必要書類の詳細を確認したい場合には、担当課へ問合せください。
手当への反映は、原則として請求する日の属する月の翌月分からとなります。また、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとなります。ただし、第2子以降出生の場合は、出生日の翌日から15日以内に新規認定手続きを行うことで、出生日の属する月の翌月分から手当が支給されます。(15日特例)
|
該当となる場面 |
届出の種類 |
|
額改定認定請求書 |
|
額改定届 |
(児童が残る国内へ残る場合には、別途新規認定手続きが必要)
|
支給事由消滅届 |
|
変更届 |
|
変更届 別居監護申立書 |
3人以上児童がいる方 |
監護相当・生計費の負担に ついての確認書 |
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年6月分の手当から現況届の提出は原則不要になりました。ただし、以下の方は引続き現況届の提出が必要です。該当する方には例年通り現況届及びその他必要書類を送付します。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 18歳年度末から22歳年末までの児童が就職している方
- その他、提出の案内があった方
よくある質問
児童手当について、お問合せいただくものをまとめました。以下のページリンクからご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
保険年金課医療手当グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5732(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2144・2145
ファクス:0572-25-7286