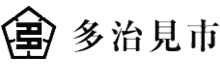ここから本文です。
更新日:2025年5月9日
堆肥化センター
はじめに
本市ふるさとクリーン村
該当地区「池田南地区」は、愛知県境である弥勒山・道樹山の麓に位置し、自然豊かな農村集落として栄えてきました。しかし集落の周囲は大半が山林であるため、廃棄物処分場や採石場が多く立地しているのが現状であります。
地元では農業生産法人を中心に、安全・安心・健康な農産物を消費者へ提供するために「ぎふクリーン農業」による、環境保全型、循環型農業を推進しています。
また、自然環境についても、地区内にはクロメダカの自生地があり、生息地の保全活動やビオトープづくり等地域住民が身近な自然を育む活動に取り組んでいます。
循環型社会システム構想
平成11年に策定し、「脱焼却・脱埋立」を最終目標に掲げ、資源の循環の取り組みを進めてきました。特に、有機性資源リサイクルシステムの検討のなかから、この池田南地区にバイオマス利活用施設(堆肥化センター)を立地させる整備事業が計画され、整備してきました。
対象地域における関係者を含めたこれまでの検討状況
循環型社会システム構想において、生ごみの資源化が大きな課題であると位置づけられました。この課題の解決のため、農政サイドおよび環境サイドのそれぞれで検討が始められ、特に、農政サイドでは、学校給食調理場から排出される食品残さに着目し、この堆肥化システムと施設について協議を重ねてきました。
施設の立地については、早い段階で池田南地区が候補にあがっており、当地区の営農組織や自治組織と、施設に関する説明や意見交換を繰り返し行ってきました。
現在、当施設は「池田南ふるさとクリーン村構想」で構想の核的施設と位置づけ、資源の循環に寄与していくものであります。
期待される効果
堆肥化センターで生産される堆肥は、地区内の農地に還元され、安心・安全な農産物の生産が可能になります。
この農産物が直売所や学校給食に提供されることで、地産地消が推進され、食育教育にもつながっていきます。
全量焼却から堆肥化への転換は、二酸化炭素の発生量を大きく抑えることができ、温暖化防止に寄与します。
BDFの利用は化石燃料の消費を軽減し、資源の有効利用に寄与します。
施設の管理運営や利活用の場で、この地区の住民の交流と協働が進み、地域の活性化に寄与するとともに、新たな雇用の創出も期待できます。
関連する計画策定等
- 平成10年度 多治見市循環型社会システム構想策定(環境庁の100%補助事業)
- 平成12年度 給食センターから排出される有機性廃棄物堆肥化リサイクルシステム構想(報告書)策定
- 平成13年度 有機資源堆肥化センター整備運営基本計画(報告書)策定
- 平成16年度 池田南地区ふるさとクリーン村構想策定(17年3月4日認定)
- 平成17年度 バイオマス中期利用計画策定
施設整備の状況
平成16年度
- 三の倉町地内に、市単費にて堆肥化センター用敷地(1,400平方メートル)を造成。
- 施設の管理運営について、池田南営農組合と協議。
平成17年度
- バイオマスの環づくり交付金を確保し、堆肥舎、BDF棟を建設、堆肥化プラント及びBDF製造施設を建設(17年12月完成)。
- 食品残さや廃食用油の収集運搬体制を整備。
- ふるさとクリーン村協議会にて利活用の推進を図る。
- プラントの試運転と従事者の研修を実施(18年1月~3月)。
堆肥化センターの施設概要
- 堆肥舎(鉄骨造平屋243平方メートル)
- 堆肥化プラント(1次発酵機1基・自動投入機1基)
- 堆肥熟成槽
- 事務所
- 合併浄化槽
- BDF製造棟(鉄骨造平屋50平方メートル)
- BDF製造施設
- 給油装置
- 保管庫
整備費内訳
- 敷地造成費 30,163千円
- 建設費 26,605千円
- 機械設置費(堆肥化プラント 16,464千円・BDF製造施設8,138千円)
- 備品類(専用コンテナ等)3,376千円
- 総事業費 84,746千円
バイオマスの収集、輸送方法
池田南地区の家庭から排出する生ごみは、ステーションに専用コンテナを配置し、これを収集トラックにて回収する。また、学校給食調理場で発生する食品残さは、専用コンテナにストックし、収集トラックにて毎日回収する。
廃食用油の回収は、市内全域で分別収集が確立しているので、学校給食調理場からの回収を新たに追加することで対応する。
対象とするバイオマスと変換量、変換方式
堆肥化プラント
- 池田南地区の家庭から排出する生ごみ(135世帯・421人)0.1t/日(35t/年)
- 学校給食調理場等で発生する食品残さ 0.9t/日(215t/年)
変換方式・・・好気性高熱菌による高速発酵
BDF製造施設
- 池田南地区の家庭で分別された廃食用油 70L/年
- 市内の一般家庭で分別された廃食用油 15,930L/年
- 学校給食調理場で発生する廃食用油 14,000L/年
変換方式・・・メチルエステル化法
BDFの年間生産量 27,000L/年
堆肥化に必要な副資材
堆肥化の主材料である食品残さは水分含有量が多いため、水分調整用の副資材が必要となり、もみ殻・稲わら・木材チップ等の未利用バイオマスで対応することになる。
バイオマスの利活用先
堆肥は主に池田南地区の農地に還元、BDFは池田南地区で使用される農耕用機械および収集車の燃料としての利用を予定しており、池田南地区ふるさとクリーン村推進協議会でその利活用を推進していく。
バイオマスの変換に伴って発生する残さ
堆肥化プラントからは、投入する副資材の性状によっては、熟成の過程で残さが出る可能性はある。しかし、すべてを「もどし堆肥」として再利用できるので、施設外に残さが出ることはない。
BDF製造施設からは、メチルエステル化反応の過程でグリセリンが分離するが、発生したグリセリンは堆肥の原料として処理又は焼却処理する。
生産された堆肥やBDF
池田南地区ふるさとクリーン村推進協議会が受け皿となり、利活用の調整、および農業者等の利用促進を図る。
堆肥とBDFの生産実績
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
三の倉センター管理グループ
〒507-0045 多治見市三の倉町猪場37
電話:0572-23-1103
ファクス:0572-25-4010