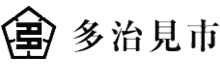ここから本文です。
更新日:2025年7月29日
住宅改修
介護保険の認定を受けている被保険者の方が、事前に市に申請したうえで、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたときに、介護保険から改修費の一部が支給されます。
この住宅改修制度についてご案内します。
令和7年4月から従来の住宅リフォームヘルパー派遣制度を廃止し、「有資格者による理由書」の作成制度を開始します。
詳細はこちらをご覧ください(「有資格者による「住宅改修が必要な理由書」の作成について」のページを表示します)。
また、多治見市では被保険者の方に提供する有資格者を有する事業所様の一覧を作成・掲載しています。必要に応じてご活用ください。
住宅改修理由書作成有資格者事業所等一覧(PDF:461KB)
掲載を希望される事業所様はこちらをご覧ください(「住宅改修理由書作成手数料支払制度について」のページを表示します)。
介護保険での住宅改修とは
介護保険の要支援1、2・要介護1~5と認定された方の生活環境を整えるための手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な住宅改修に対して、改修費用の7割から9割が住宅改修費として介護保険から給付されます。
対象となる住宅
被保険者本人の住民票上の住所がある住宅のみが対象となります。
一時的に身を寄せている住宅や同じ敷地内にある別の住宅は対象となりません。
住宅改修費の支給額
介護認定を受けている被保険者の方の住民票の住所のある住宅の改修費用について20万円を上限として、改修費用の7割から9割を支給します。
20万円を超えた費用は全額自己負担となります。
対象になる住宅改修の内容
- 手すりの取付け…廊下・トイレ・浴室・階段・玄関・玄関から道路までの通路などに設置
- 段差の解消…居室・廊下・トイレ・浴室・玄関等の各部屋及び玄関から道路までのスロープの設置
- 滑りの防止のための床材の変更…居室を畳から板張りに、浴室の床を滑りにくいものに変更
- 引き戸等への扉の取替え…開き戸を引き戸等に取り替え、ドアノブの変更や戸車の設置
- 洋式便器等への取替え…和式便器を洋式便器に取り替える場合
- その他工事(上記1~5の工事に伴うもの)
- 手すり取付けのための壁の下地補強
- 床材の変更のための下地の補修や通路面の材料変更のための路盤整備
- 扉の取り替えに伴う壁や柱の改修
- 便器の取り替えや浴室の段差解消に伴う給排水設備工事
但し、住宅の新築や増築(新たに居室を設ける等)、老朽化に伴う改修は給付対象外となります。
受領委任払い制度
介護保険における住宅改修費の給付について、多治見市では、償還払い制度に加え、令和3年4月から受領委任払い制度(登録事業所のみを対象)を導入し、両制度を併用しています。
「受領委任払い」とは、被保険者から、保険給付分の受領を施工業者に委任することにより、被保険者は、施工業者に負担割合に応じた額を支払い、保険給付分については市から直接施工業者に支払うものです。「受領委任払い」の適用を受けるには、多治見市に登録のある施工業者により、住宅改修を行う必要があります。
受領委任払い制度についてはこちらをご覧ください(「住宅改修費の受領委任払い制度」のページを表示します。)
住宅改修の手順
1ケアマネジャーなどに相談
住宅改修を行う前に必ず担当のケアマネジャーまたは高齢福祉課に相談してください。
介護サービスの利用がないなど、担当のケアマネジャーがいない場合は、こちらを確認してください。
2施工業者の選択、見積もり依頼
複数の業者に見積依頼を行い、工事費の適正化に努めてください。
受領委任払い取扱登録事業所一覧…登録事業者以外の業者でも、償還払いでの申請できます。
3高齢福祉課へ事前申請
必要書類を高齢福祉課(駅北庁舎2階)へ提出します。
住宅改修費の支給には、工事着工前に市に事前申請をしていただき、事前承認を受ける必要があります。事前承認がない場合には、保険給付の対象となりませんのでご注意願います。事前申請が困難な場合は、高齢福祉課にご相談願います。
申請に必要な書類
- 住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーや福祉住環境コーディネーター等が作成)、ケアマネージャーがいない場合はこちらを確認してください。
- 改修前の住宅の間取り図…対象者の生活動線を朱書きしてください(余白に申請者名を記入)
- 改修後の住宅の間取り図…改修箇所を記載してください(余白に申請者名を記入)
- 工事費見積書(申請者宛のもの)
- 改修前の日付入りの写真(余白または裏面に申請者名を記入)
- 住宅改修承諾書(住宅の所有者と改修の申請者が異なる場合のみ提出)
- 受領委任払い委任・同意書(受領委任払いの場合のみ提出)
- 上記の1・2・7・8の様式は申請書ダウンロードのページをご利用ください
有資格者による理由書の作成
ケアマネージャーがいない等の理由により、「住宅改修が必要な理由書」の作成が困難な場合は、有資格者による理由書の作成が必要です。詳しくはこちらからご確認ください(「有資格者による住宅改修が必要な理由書の作成について」のページを表示します)。
また、必要に応じて以下の一覧をご活用ください。
住宅改修理由書作成有資格者事業所等一覧(令和7年4月1日現在)(PDF:454KB)
一覧についてお知りになりたい事業所様はこちらをご覧ください(「住宅改修理由書作成手数料支払制度について」のページを表示します)。
4申請結果の連絡
事前申請の書類が提出されると、高齢福祉課で住宅改修の内容の確認をします。
確認後、高齢福祉課から申請者の方に「事前申請承認通知書」を送付します。
同時に、高齢福祉課から「住宅改修が必要な理由書」を作成したケアマネジャーもしくは福祉住環境コーディネーター等にも、電話にて事前申請が承認されたことを連絡します。
この通知、連絡があった後に、改修工事を実施してください。
結果の連絡には7~10日程かかります。