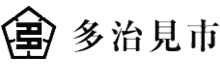ここから本文です。
更新日:2025年8月29日
保険料・納付
65歳以上の方が負担する介護保険料は各市町村の状況に応じて3年ごとに見直すことになっています。
多治見市高齢者保健福祉計画に基づき見直した結果、令和6年度~令和8年度の保険料の月額基準額は5,950円となります。
三菱UFJ銀行の窓口における介護保険料納付の取扱い終了について
三菱UFJ銀行窓口における、多治見市が発行する納付書(納税通知書・納付(納入)通知書)の取扱いは、令和6年3月31日をもって終了しました。
ご不便をおかけいたしますが、令和6年4月1日以降、納付書による窓口納付は、他の金融機関窓口をご利用ください。
納付書に取扱金融機関として「三菱UFJ銀行」の印字がある場合でも、窓口での支払いはできません。
口座振替は、これまで通り三菱UFJ銀行の口座が利用可能ですので変更等のお手続きは不要です。
なお、「地方税統一QRコード」が記載されている納付書に限り、令和6年4月以降も引き続き三菱UFJ銀行の窓口にて納付が可能です。
多治見市指定金融機関等の一覧はこちらをご覧ください。
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
所得に応じて保険料が異なります。
| 所得段階 | 対象となる方 | 保険料率 |
保険料 |
|---|---|---|---|
|
第1段階 |
生活保護受給者、住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者及び住民税非課税世帯で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9,000円以下 |
基準額×0.285 |
20,340円 |
|
第2段階 |
住民税非課税世帯で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下 |
基準額×0.485 |
34,620円 |
|
第3段階 |
住民税非課税世帯で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える |
基準額×0.685 |
48,900円 |
|
第4段階 |
住民税課税世帯かつ本人住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9,000円以下 |
基準額×0.90 |
64,260円 |
|
第5段階 |
住民税課税世帯かつ本人住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9,000円を超える |
基準額×1.00 |
71,400円 |
|
第6段階 |
本人住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満 |
基準額×1.15 |
82,110円 |
|
第7段階 |
本人住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 |
基準額×1.30 |
92,820円 |
|
第8段階 |
本人住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 |
基準額×1.50 |
107,100円 |
|
第9段階 |
本人住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満 |
基準額×1.70 |
121,380円 |
|
第10段階 |
本人住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上420万円未満 |
基準額×1.80 |
128,520円 |
|
第11段階 |
本人住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 |
基準額×1.90 |
135,660円 |
|
第12段階 |
本人住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 |
基準額×2.00 |
142,800円 |
| 第13段階 | 本人住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上700万円未満 | 基準額×2.10 | 149,940円 |
| 第14段階 | 本人住民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満 | 基準額×2.30 | 164,220円 |
| 第15段階 | 本人住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上 | 基準額×2.40 | 171,360円 |
課税年金収入額:公的年金の収入額のことです。遺族年金・障害年金は非課税所得であるため、遺族年金・障害年金の収入額は保険料の算定には用いません。
合計所得金額:収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ただし「合計所得金額」から「長期譲渡所得および短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除」及び「公的年金等に係る雑所得を控除(所得段階が第1~第5段階のみ)」した金額を用います。
第1段階から第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額(控除後の額が0円を下回る場合は0円)で算定します。
基準額の推移
- 平成24年度~平成26年度 4,826円
- 平成27年度~平成29年度 5,200円
- 平成30年度~令和2年度 5,950円
- 令和3年度~令和5年度 5,950円
- 令和6年度~令和8年度 5,950円
納付方法
保険料の納め方には、年金からの天引きによる特別徴収と、納付書や口座振替による普通徴収の2種類があります。
|
種類 |
対象者 |
納付方法 |
|---|---|---|
|
特別徴収 |
年額18万円(月額15,000円)以上の年金を受給している方 (天引きの対象となる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です) |
年6回の年金支払いの際に天引き |
|
普通徴収 |
特別徴収以外の方 |
多治見市が送付する納付書または口座振替 (口座振替を希望される方は別途お申込が必要です) |
基本的に介護保険料は特別徴収で納めていただきますが、年額18万円(月額15,000円)以上の年金を受給している方でも、下記の場合は納付書で納めていただくことになります。
- 年度途中で65歳になった
- 年度の途中で他の市町村から転入した
- 収入申告のやり直しなどで、保険料の段階区分が変わった
- 年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった
- 受給している年金の種類が変わった
- 年金担保、年金差止、現況届の未提出などで、年金が停止し、保険料が差し引きできなくなった
納付書払い
普通徴収で納付書払いの方は、納付書をお持ちになり、金融機関の窓口や市役所高齢福祉課もしくは地区事務所の窓口で納めてください。
また、納付書裏面に記載されているコンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリによる納付もご利用いただけます。
4月の仮算定時には4月~7月分、8月の本算定時には8月~翌年3月分の納付書をお送りします。
口座振替
普通徴収の方は、口座振替をご利用いただくと、保険料の納め忘れがなくなり便利です。口座振替のお申し込みは、預貯金口座をお持ちの金融機関の窓口や高齢福祉課もしくは地区事務所の窓口で受け付けております。納付書、通帳、印鑑(金融機関届出印)をお持ちになり、お手続きください。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の介護保険料
加入している医療保険の算定方法により、保険料が決まります。
国民健康保険に加入している人
国民健康保険料の算定方法と同じように、世帯ごとに決められます。
介護保険料は、所得割、均等割、平等割をもとに算定します。
|
所得割額 |
所得に応じて計算 |
|
均等割額 |
各世帯の第2号被保険者に応じて計算 |
|
平等割額 |
第2号被保険者のいる世帯、1世帯あたりで計算 |
納付方法
国民健康保険料と介護保険料を合わせて、一括して世帯主が納めます。
職場の医療保険に加入している人
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。原則として事業主が半分を負担します。
納付方法
医療保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から納めます。
保険料の減免
災害により住宅や家財に著しい損害を受けた場合、世帯の生計を主として維持する方が死亡または長期の入院をされた場合、失業、事業の休廃止などにより収入が著しく減少した場合などで、収入の著しい減少のため生活が困難となり、利用できる資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず支払いができないと認められる場合は、保険料の減免を受けることができる可能性があります。
詳しくは高齢福祉課までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
高齢福祉課介護運営グループ・介護資格グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5826(介護運営グループ)・0572-23-5211(介護給付グループ)
内線:2240~2247
ファクス:0572-25-6434