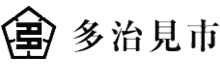ここから本文です。
更新日:2025年7月1日
保険料・納付(後期高齢者医療制度)
保険料
保険料の計算方法
保険料は、「一人当たりの定額の保険料(均等割額)」と「所得に応じた保険料(所得割額)」を合計した額です。所得に応じ、公平に保険料をご負担いただきます。
保険料=均等割額+所得割額
令和6・7年度の均等割額は被保険者一人当たり49,412円で、所得割率は9.56%です。所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に、この所得割率を乗じた額になります。
なお、保険料の一人当たりの上限額は80万円です。
保険料の軽減
所得により、均等割額を軽減する制度があります。
均等割額の軽減
世帯主および世帯に属する被保険者の所得の合計額に応じて、均等割額が軽減されます。
所得とは、給与所得者の場合は「給与収入額」から「給与所得控除額」を差し引いた額、年金受給者の場合は「年金収入額」から「公的年金等控除額」を引いた額(65才以上の方のみ特別控除額15万円を適用)です。
|
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額※1 |
軽減割合 |
|---|---|
| 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等※2の数-1)以下 | 7割 |
| 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等※2の数-1)+30.5万円×(被保険者数)以下 | 5割 |
| 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等※2の数-1)+56万円×(被保険者数)以下 | 2割 |
1 軽減の基準となる「10万円×(給与所得者等の数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
2 一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で125万円超または65歳未満で60万円超)。
被用者保険の被扶養者であった人の軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった人は、所得割額の負担はなく、均等割額が制度に加入後2年経過する月までの間に限り5割軽減されます。(ただし所得が低い人に対する軽減にも該当する人については、いずれか大きい軽減が適用されます。)
被用者保険とは
協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称(国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。)
納付方法
普通徴収
年金からの天引きとならない方は、納付書や口座振替により、7月から3月までの9回に分けて納めていただきます。
納付書払い
納付書をお持ちになり、金融機関の窓口や、指定のコンビニエンスストア(バーコードの印字があるものに限る)で納めてください。市役所、地区事務所でも納めることができます。
口座振替
口座振替にすると、保険料の納め忘れがなくなり便利です。口座振替のお申し込みは、預貯金口座をお持ちの金融機関の窓口、保険年金課、地区事務所で受け付けています。資格確認書、通帳、印鑑(金融機関届出印)をお持ちになり、手続きをしてください。
※従前の国民健康保険で口座振替登録があった方も再度手続きが必要です。
特別徴収
年金受給額が年額18万円以上の人は、年金からの天引き(特別徴収)となります。ただし、次の基準に該当する場合は年金からの天引きとなりません。
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える場合
- 介護保険が年金からの天引きを行っていない場合
- 資格を取得した当初の時期
なお、年金からの天引き(特別徴収)を、ご本人または世帯主、配偶者などの口座振替に変更することもできます。
口座振替を希望される場合は、保険年金課までお問い合わせください。
お問い合わせ
保険年金課年金国保グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2164・2165
ファクス:0572-25-7286