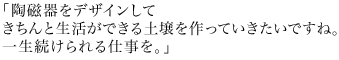現在、株式会社深山の取締役であり商品開発室室長の柴田正太郎さん。 先日は第9回国際陶磁器展美濃デザイン部門銅賞を同社製品でデザインを担当した「sasasa~サササ~」で受賞されました。精力的に活動されている陶磁器デザイナーの柴田さんにお話を伺いました。
□深山では、どのように製品はできてくるのですか?
大きく分けて2パターンあります。一つはオリジナルの商品ですね。 これらは地元や、東京などの消費地、そして海外で行われる展示会での発表へ向けて作っています。 地元の展示会の場合だと、作ったものに他社で絵柄をつけて販売される場合もあるので、絵柄がつけやすいシンプルなものや、ギフト用として定番アイテムとなる取り皿は、必ずシリーズの中に組み込む事などを意識しながら作ります。 消費地向けには、家庭使いのものだと白色だけではなく季節感や素材感がさらに伝わるような色も足したり、業務用食器は料理のキャンバスとなるように作ったりしています。 もう一つはOEMといって依頼企業のブランドとして作る場合です。基本的には提案されたデザインを基に、当社で生産可能な形状に修正して作ったりするのですが、場合によってはデザインそのものから提案させていただく事もあります。最近では品質の高さを認められ、是非深山だから作って欲しいという依頼も多く、自社のブランド力をあげていく意味でもOEMは外せない要素ですね。

hasu(2009)
□製品の形状だけではなく会社のブランド力をあげていく事も目的になっているんですね。
例えば今回の受賞作品の「sasasa~サササ~」は、焼き締め(釉薬がかかっていない状態)の製品ですが、当社の白磁は美しさを求めて高温焼成した結果、表面がガラス化して汚れがつきにくくなり、釉薬がかかっていなくても食器として使っていただくことができます。1330℃の高温焼成をし、綺麗に仕上げる技術はあまり他のメーカーではできない事ですし、こういった自社のものづくりの個性を活かして他社と差別化していく事は日々考えています。
□「sasasa~サササ~」の開発の経緯を教えてください。
もともとは海外の展示会用に開発したものです。 当社ならではの素地の美しさと薄さを伝えようと思い、焼き締めにして、その素材の魅力が伝わりやすい様に、直接手に触れるアイテムとしてカップを作ったのが最初です。 銅版転写による釉薬での加飾は、他の製品に使われていた技法なのですが、マットな質感の中にも光沢が欲しかったのでこのシリーズに用いました。 僕は、会社での商品開発以外にもコストや生産方法の面で商品にできないようなものは、自分自身の作品として制作を行っていますが、焼き締めを食器に活かすきっかけはこういった制作からヒントを得ています。商品開発と個人的な制作はリンクする部分が大きいですね。

第9回国際陶磁器展美濃 デザイン部門銅賞 受賞“sasasa~サササ~”(2009)
□柴田さんは地元多治見市出身ですが、意匠研を志望した理由は何ですか?
家業が陶磁器の上絵付けの仕事をしていたというのが大きかったと思います。
小さい頃は実家の手伝いをさせられる事も多かったのですが、やきものの仕事は本当に、暑いし、重いし、嫌いでしたね。だから多治見から離れてやきもの以外の仕事がしたいと思い、家具の営業の仕事に就きました。営業職でしたが、ただ売り込みに行くだけではなく、入社後すぐに図面の描き方や、セールス用のプレゼンボードの作り方まで教えてくれるような会社でした。
約5年間勤め、仕事自体は順調だったのですが、自分のメンタリティが変化してきたのですかね、次第に自分自身でも何か作り出す仕事がしたいと思うようになってきました。
その頃には、やきものに対してもかつての拒否感は薄れていて、地元に帰りたいという気持ちも強くなってきたので、意匠研に入所しようと決めました。
□意匠研時代に印象的だった出来事はありますか?
1年生の秋頃に陶磁器デザイナーの森正洋先生がたまたま意匠研に立ち寄られ、僕の作品を見ていただいた事ですね。
入所してみると、同級生には経験者が多く何でも器用に作っていて引け目を感じる部分がありました。
その時に、森先生から「不器用だけど頑張れば何とかものになる。」とおっしゃっていただいて、頑張るきっかけをいただいた気がします。自分の作品を初めて認められたような気持ちでしたね。そこからは自分が同級生にどこで勝てるかを探して、勝てる所で勝負するつもりで毎日制作しました。
森先生の言葉は自分を勇気付けるためにはとてもありがたかったと今でも思います。
□仕事をしていて、やりがいを感じるのはどのような時ですか?
入社して間もない頃にデザインした「perito~ペリート~」というシリーズの製品が、店頭に今でも置かれているのを目にするとうれしいですね。
自分の仕事が社会と繋がっていると実感できる瞬間です。その喜びがあるから続けられている気がします。最近では自分にも後輩ができてきたので、彼らにもそういった喜びをこれから感じていって欲しいですね。そのためにもただデザインするだけではなく、見せ方や売り方まで一人一人が判断できるように育てていきたいと思っています。
□今、深山は意匠研の研究生が憧れるクリエイティブな会社になっていますが、研究生の頃から「高いデザイン性で有名なフィンランドの陶磁器メーカーであるアラビア社のようなものを日本にも作りたい。」とおっしゃっていましたよね。全国から集まってきてくれた人達が、やりがいを持って仕事を続けられる仕組みを作っていくのも、柴田さんの目指すところなのでしょうか?
この産地で生まれ育ったし、やはり何か残したいですよね。
慣れ親しんだ陶磁器という産業の分野で良いものを作っていきたいと、当時から思っていました。
意匠研に入って、同級生は地元の陶磁器関係の後継者だけではなく、わざわざ全国からやきものを学びに来ている人が多く、やきものには大きな魅力があるのだと再認識したんです。でも卒業して何年か経つとそういった人達が、会社を辞めたり、制作を続けられなくなったりして、多治見から離れていってしまう事も多くて、寂しさを感じました。せっかく優秀な人達が集まって来ているので、この産地に残って続けられる環境作りも今後は必要になってきていると思っています。
例えば、若いデザイナーが、入社後すぐに売れる商品を作ってしまったりする事もありますが、それは作り手と消費者の年齢がたまたま一致しているからだけで、継続するようなものではない気がします。経営者によっては、あえて使い捨てで、そういう若者を雇用している部分も否めません。
デザインというものは、やはり様々な経験をし、段取りを踏まえてやるべき事だと思うのです。
陶磁器をデザインしてきちんと生活ができる土壌を作っていきたいですね。一生続けられる仕事を。
(2011年10月取材)