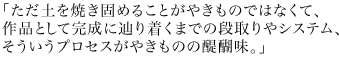多治見市陶磁器意匠研究所を代表する卒業生で国際的に活躍する陶芸家の板橋廣美さん。 従来のやきもののプロセスを見つめ直す中から新しい技法や技術を生み出し、常に挑戦的な作品を発表し続けています。近年では金沢美術工芸大学や当研究所でも教鞭をとられている板橋さんに、お話しを伺いました。
□初めに陶芸を志したきっかけは何ですか?
もともと子供の頃から作る事が好きで、陶芸に興味を持ったのは、中学校の修学旅行で1000円の抹茶茶碗を買ったことがきっかけでした。 実際にやきものを作り始めたのは大学生の時に陶芸教室に通ってからですね。大学卒業後は3年間板前のような仕事をしていましたが、どうしても一度は本格的にやきものを習ってみたいと考えていました。 やきものの勉強が出来る場所を色々と調べたら、伊藤慶二先生が多治見市陶磁器意匠研究所(以下意匠研)で講師をされていることを知り、ここしかないと思い意匠研に決めたのです。 当時はクラフト運動がとても盛んで、独特な美濃のクラフト作品にとても魅力を感じていました。
□意匠研に入ってからの研修はいかがでしたか?
まず意匠研に入って、やきものの範囲の広さを知ってショックを受けましたね。 先生方も一生懸命教えて下さり、入所して1年目はデッサンや絵付け、デザイン概論など、陶磁器デザインに対する基礎をしっかり教えてもらいましたよ。授業以外の時間には自由に実習室が使えて、当時は夜遅くまで作業が出来る環境でした。自分のやりたい事、やりたいと思う事が自由に出来たので、とにかく毎日が楽しかったです。

白の連想 (1987)

重力内無重力(1995)
□意匠研で教わった事は今でも参考になっていますか?
とても参考になっていますよ。 意匠研の時のノートは何度も見返しているので大部分は頭に入っていますが、自分の財産になっています。聞けば何でも教えてくれる先生ばかりでしたし、疑問を持った分だけ得をするといった環境でした。私は他の人よりも2、3倍は聞きましたよ。当時から何か新しい事をしないと意味がないと思っていましたから、色々な事に挑戦しました。意匠研には人がやっていない事や、新しい事をやらせてくれる雰囲気がありました。周りに真剣にものづくりに取り組む仲間がいるというのは刺激になりますよね。 デザインの授業を受けていた時でも、次の時代という事がデザインですから、“今”は作っていなかったです。皆が“未来”を考えて作っていましたよ。
□板橋さんの作品は常識的な技術を打ち破る挑戦から生まれているように思うのですが、新しい方法を次々と生み出す事ができるのは何故でしょう?
昔から新しいものを作りたいという意識がとても強かったように思います。新しい作り方をすると必ず新しいものが生まれるのですよ。過去に作られた良い作品はすでに存在しているので、それを目指して作るというよりも、別の視点からそれを超えるような新しい作品を作りたいと思っていました。 陶芸の常識では考えられないような事を試したり、一方の側面だけではなく、常に新しい側面からものを作ることを意識しています。 手を動かして絶えず実験と制作の間を行き来して、それが新たな創作につながるのではないかと考えています。
□道具を作ったり仕掛けを作ったりと、そういうことにも面白さを見出して制作されている印象を受けるのですが。
ただ土を焼き固めるのがやきものではなくて、作品として完成に辿り着くまでの段取りやシステム、そういうプロセスがやきものの醍醐味なので、そこの部分はとても楽しみながら制作しています。 それはプロセスを自分の経験の上から開発していくという事ですし、そのプロセスがしっかりしていないと求める作品ができないと思います。 景気が悪くなってきてからというもの、「売れる」とか「売れない」といった話が多くなったように思います。 意識がどんどん現実的になって、いつの間にか制作の自由が奪われてしまっているように感じます。制作において私はいつも自由でいたいですね。やきものの範囲も狭まってきている気がするので、ジャンルに縛られずにもっと広がりのある考え方をすれば良いと思います。
□若い人が卒業後に自分で頑張って陶芸家として食べていこうと思うと、売れるものという事をどうしても意識してしまうかもしれません。
私自身は自分の作品制作においては作品が売れるという事を考えていないですね。 40年も前ですが、意匠研で勉強していた時は売れるものを作ろうと思った事は一切なかったです。当時、伊藤慶二先生の授業で、箸置きの課題が出たときに「土を握って置いてみろ」と言われたのです。手の握り方で形が変わる事、ねじったり、ひっぱったり、そういう課題だったのです。お魚の箸置きを作った子が「でも、これ売れますよ」と反論したら、先生に「誰が売れるもの作れと言った!」と怒られましてね(笑)。今は厳しい時代ですね。
□それは怒られますね(笑)。
“重たい鉢”という轆轤の課題が出された時も、実際食器は軽い方が良いだろうと思っていましたし、みんな普通の鉢を重く轆轤でひいて提出したのですね。 でも先生からしたら全部ダメなのですよ。要は鉢としての機能なんてほんの少しで良くて、へこんでいれば器になるし、土の塊を押すだけでも機能が生まれるって事をおっしゃりたかったんですね。 “うつわ”というもの自体を考える課題だったように思います。伊藤慶二先生の授業で教わったのは、土の表情を見つけたり、形を作るだけじゃなくて、土から学ぶという事でした。

Assosiation with white(2006)
□現在は金沢美術工芸大学において教鞭をとられたり、意匠研にも講師としてお越しいただいていますが、若い人を指導される上でどういった点を大事にされていますか?
やはり基礎的な事がとても大事だと思います。基礎がしっかりしていると、自分がブレずにいられるのではないでしょうか。 意匠研なら基礎をしっかり教えてもらえる場所ですし、技術が先行しても自分に必要な技術を選択すれば良いと思います。それは、高校を卒業したばかりの人から、美術大学出身の人、サラリーマンをしていた人まで色々な経歴の人が集まっているので、色々な選択が出来るのだと思いますね。 ただ、美術大学が技術の学校になってはまずいですね。美術大学ではほぼ全員がやきものをゼロから始めるので、そこで技術の話ばかりだと凝り固まってしまいます。考えが成熟する前に技術を覚えてしまうと、どうしても技術ばかりが先行してしまうのです。美術大学では技術を教えずに基礎を教えるという非常に難しい部分があります。意匠研と美術大学とはシステムも役割も違いますが、自分が土とどう関わっていくのかという事は共通して探していって欲しいですね。
□大学でもご自身の制作はされているのですか?
今は本当に時間がないですね。教える時間と、会議の時間と、研究会の時間と。実際に作る環境は大学にはあまりないです。でも色々と仕事はいただくので、東京の仕事場に戻ってから制作しています。
□最後に、これからやきものの道を志す人達に伝えたい事はありますか?
やきものと良い出会いをして、やきものを好きだという事が大事だと思います。 スタートは何でも良くて、茶碗でも壷でも興味を持つ良いきっかけがあれば自然とそこから発展していきますから。漠然としているよりは、一つのやきものに興味があったり、特定の作家の作品を好きだとか、やきものの何に興味を持ったかという事を、自分の中にしっかり持っている事が大事だと思います。 また、やきものを知っていく事によって、自分の生活のスタイルが大きく変わるので、自分の幅が広がります。物を選ぶ事と作る事は同じ時限なので、器一つ買うにしても意識を持つようになります。やきものに興味を持ったら制作も含めて、自分でやきものを理解しないと駄目ですね。 意匠研はそれができる場所だと思います。
(2011年11月取材)