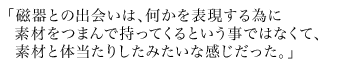磁器という素材と出会い、大胆な作品を国内のみならず海外でも数多く発表されている陶芸家、加藤委さん。多治見市陶磁器意匠研究所を代表する卒業生である加藤さんに、これまでの活躍の軌跡と日々の制作に対しての姿勢についてお話ししていただきました。
□現在どのようなペースで制作をされていますか?
年間に5、6回ある個展を中心に制作しています。 個展に向けての作品の制作以外にも、自分の『肥やし』となるものを得ながら、探りつつという感じです。
□『自分の肥やしとなるもの』というのは何ですか?
それは次の新たな作品を生み出すための言わば『引き出し』の様なものです。 ただ生活を支える為に作品を制作するという事だけではなく、それ以上に追求したいものがありますから。技術などの問題の前に『生きていく』という精神的な部分の中から発見することの方がずっと大きいと思います。

気さくにインタビューに答える加藤さん
□「技術」とおっしゃいましたが、加藤さんにとっての「技術」とは何ですか?
とても基本的な事がベースとなっています。
その多くが意匠研究所で学んだ事ですし、それがあるからこそやっていけるのだろうと思っています。 意匠研究所には十代の若い時に入所したので、出会う人、見る物、技術的な事など初めての事ばかりでした。
□加藤さんが研究生の頃の事を教えて下さい。
全国から若者が集まっていて、とても刺激的でした。
先輩には現在、金沢美術工芸大学の教授である板橋廣美さん、講師には伊藤慶二先生、非常勤講師には熊倉順吉先生といった方がいました。
研究生はデザインとクラフトというコースに分かれていて、僕はデザインのコースだったので、上絵付けのデザインなどを学んでいました。意匠研究所は上絵付研究所が前身で、技術的な人材を育成して地場産業へ送り出していましたから、当時は陶芸家の育成場所という感じではなかったですね。「陶芸家にはなるな。」と言われたほどです(笑)。
□意匠研究所を卒業してからはどうされたのですか?
卒業後は製陶所に就職しました。土練機で粘土を練ったり、機械轆轤でペタンキューといった機械的な作業が多い仕事でした。半分はバイクで遊びほうけていましたけど(笑)。
□その頃は陶芸家になろうと思っていたのですか?
その頃は陶芸家になるなんてそんな気は全く無かったです。ただ、物を作って生活が出来たらいいな、という夢はありました。バイクで各地を旅しながら、色々な生き方があると感じて、自分自身の道を進まないと駄目だと思いましたね。それで思い切って会社を退職しました。
真っ白な磁器との出会いはちょうどその頃でした。青磁をやりたいとか、こういう様式のものやりたいとかではなく、自分のやっていきたい素材だと直感しました。
□素材との出会いがとても大きな一歩だったのですね?
そう、今でも鮮明に覚えてます。
工場の部屋いっぱいにドーンって磁器が置いてあるんですよ。磁器の白さに自分が吸い込まれていくような感じで、それを見た瞬間に圧倒されましたね。
最初は轆轤を挽いてみてもほとんど形にならなくて、それがまたとても新鮮で、もう毎日『土と格闘する』という日々でした。何かを表現する為に素材をつまんで持ってくるという事ではなくて、素材と体当たりした感じです。
□その後、作品が形になって陶芸家として活躍されるまでのことを教えてください。
しばらくは試行錯誤の時期が続きました。出来た作品を持ってギャラリーに売り込みに行きました。
名古屋で2、3件まわって断られて、京都も駄目でしたね。それでもう東京しかないと思って、カバンいっぱいに作品を詰め込んで、売れるまで絶対帰って来ないつもりで行きました。
その一軒目がサヴォアビーブルだったんです。 「多治見でやきものをしているんですけど、作品見てもらえませんか。」と。アポなしだったので作品見てもらう前に断られますよね。でも何時間も居座って、今考えると、あれは何かほとんど異常でしたよ(笑)。 その後閉店間際になってオーナーに何とか作品を見てもらえる事になったんです。
1点、2点、3点って相手の顔色見ながら出していくと、そのうちに表情が変わってくるのが段々わかって、「来た来たっ、感動してるぞ!」と思いましたね。「じゃあ、これを10個、これ20個 …。」と、気付いたらすごい量なんですよ。最終的には注文がわぁーっと。
□それが作家としての第一歩となるわけですね? とても印象に残る出来事ですね。
そうですね。あれがなかったら今もないですし。
その一週間後です。東京国立近代美術館の学芸員の金子賢治さんから電話があったのは。「近代美術館の金子と申しますけど、ちょっと資料送ってほしいんだけど。」って、近代美術館?国立?ちょっとビビりますよね(笑)。
そんなこと今から考えても奇跡みたいですけど。でも奇跡とか言いながらもやる気でやらないとそんなものは訪れないですよ。
若い人達には、「ただお金のため」には売り込みに行って欲しくないですね。自分の作品を純粋に見て欲しいという、体当たりする覚悟で行ってもらいたいと思います。
□造形的な作品の“フリーズフレーム”はいつ頃生まれたのですか?
岐阜県加茂郡の富加町という所に古いお寺があって、そこに工房と住居を見つけて薪窯をつくり始めたんです。釉薬が溶けて、土が焼き固まるということを自分で実感しないとダメだと思ったんです。
“フリーズフレーム”が生まれたのはちょうどその頃です。形としては皿の成形の際、石膏型に伏せて作るのですが、その伏せた皿のタラっとした部分をもっともっと伸ばしていったら面白いと思ったところからですね。

Freeze Flame (2008)

使用する道具や制作中の作品の数々
ここから数多くの作品が生み出される
□食器の発展として生まれたのですね。加藤さんにとって「食器」と「オブジェ」との境というのはあるのですか?
境目というのはほとんどないですね。造形作品を作ろうとして作っているわけではなく、作っている事自体全てが表現ですから。大きい造形作品を作るのもぐい飲みを作るのも全然変わらないですよ。精神的な部分においても。
□加藤さんは常に休み無くエネルギッシュに制作されているという印象を受けますが何がそうさせるのでしょうか?何か目指すものがあるのでしょうか?
目指すというものは全く無いですよ。誰かの上を行こうとかも無いですし。
でも『やきもの屋』でどこまで行けるかなと思い制作を続けています。やきもの屋以外に何もできないですから。やきものを通じて多くの人との関わりから、様々な事が生まれて来るから楽しいですよ。結局、人と人との繋がりがとても大きいと思いますね。
□最後に意匠研究所の後輩に伝えたいことやアドバイスはありますか?
自分がどの方向に進むべきかをまず見極める事だと思います。
そして、そこにまっすぐに突入してほしい。入口しかないトンネルの中に入って行くように、自分で掘っていくしかないと思うんです。人それぞれ色々な人生があるわけで、それぞれのトンネルをいかに掘るかという事を恐れずにどんどん挑戦して欲しいですよね。
意匠研究所に入れば陶芸家になれて、ちょっと土をひねればお金を稼げてしまう、そんなちっぽけな事ではないですから。
これから多くの若者が意匠研究所に入って来ると思いますが、とにかく意匠研究所なら研究生の間は先生をしっかり見て学んで欲しい。先生も研究生を一生懸命育てて欲しいです。そういう関係がないと、何か『良いとこ取り』みたいな中身の無い勉強になってしまうと思うんですよ。そういう作り手は、『作り手』とは言えないですよね。だから意匠研究所の先生達にも頑張って欲しいと思っています。
本当にうっとうしいくらいの熱意ですからね、若者っていうのは。
(2010年8月取材)